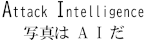 |
 清水穣氏が的確に全容を紹介している。長い引用になるが、読むだけで会場のようすが彷彿と伝わってくる。 「展示された写真群は、志賀の作品であるとともに津波後に遺された写真を演じている。それゆえ写真自体の存在と写真のなかの死者たちの存在が重ねられ、ほぼ等身大のパネルとして立てられている。 とりわけ、ランダムに反復される数々の石の写真群は、(中略)インスタレーション全体の意味が「喪」にあることを強く示唆する。(中略)写真たち=死者たちは外光=現在に背を向け、渦の中心点を向いている。(中略)その写真たち=死者たちの中に分け入る行為は自動的に「あの日あの時」へと向かうこと、「あの日あの時」を追憶することに重なるとともに、しかし写真を見るためには我々は振り返って、逆光(=現在)の中に浮かびあがる四角い闇と対峙しなければ(=喪に服さなければ)ならない。追憶と喪が交代する舞台装置として、「螺旋海岸」は実に巧みに構成されているのである。」(清水穣「写真の意味、あるいはB級ホラーの演出」) 後藤繁雄氏も彼女の成長に最大級の賛辞を贈った。後藤氏は写真集『リリー』(2007年)の編集・発行に関わられている。 「彼女がうみ出そうとしている「写真」とは何なのか? それは、「彼女にとっての現実」と言ってよい。現実を撮るのではなく、現実を生むこと。そこには普通の意味でのリアルとフィクションの区別などない。……いつもこの宇宙のどこかに人類の記憶のアーカイブがあって、そこにいきなりアクセスてしてしまったような、特別の感覚に襲われる。」(後藤繁雄RE-think現代写真論「来たるべき写真への旅」) 後藤氏は写真による写真展として、清水氏は写真を使ったインスタレーションとして、それぞれに評価されている。 後藤氏が「彼女の真実=写真にとって、リアルとフィクションの区別などない、と書き、清水氏はまさにその点に異議を唱えた。そのB級ホラー説を読む前に、志賀さんの表現手法を確かめておこう。 彼女は、「(作品の)基本はあくまで演出です」と言う。(アサヒカメラ2008年3月号) 「・・・誤解を招くかもしれないですが、今回は写真を撮るというよりも、絵を描いているような感じに近かった。1つの写真にも、レイヤーを重複させ、つまり撮影を何回も行っています。」(後藤繁雄RE-think現代写真論「来たるべき写真への旅」) 撮影を何回もとは、「いったん撮影した写真のプリントを針で穴を開けたり切り裂いたりしりして、そこに背後から光を当てて再撮影する。(中略)こうしてイメージは恩寵の光を与えられ、一つの異界として立ち上がる」。(竹内万里子「写真という生に向かって」) 清水氏は、写真が見えないものを写すことを前提に、 「写真の本質に幽霊的なものがあるということと、幽霊や心霊を文字通り写真に写し込むこととは別のことである。(中略)B級ホラーとは、そしてその通俗性とは、眼に見えない写真の幽霊性を、眼に見えるエフェクトとしてそのまんま表現することなのであり、(中略)読者も既にお気づきのように、志賀理江子の写真はB級ホラーである―と言うか、それは笑ってしまうほどにあからさまなので、私は志賀理江子の写真が受けているのはその理由によると信じて疑わなかったのだが。」(清水穣 「写真の意味、あるいはB級ホラーの演出」) 楠本亜紀さんも、仕掛けの細部に疑問を投げかける。 「男性の胸を木が突き破っているように見える写真では、上部にある木の根の先に、空から吊るしたワイヤーのようなものが見える。暗闇のなかに浮かぶ白い石の写真では、背面には色が塗られていないことがわかる。(中略)志賀の多くの写真はこうした安価な手仕事感で満ちている。」 しかし同時に、「イメージの創出者としての志賀の立場が強調されて」いて、「とても完成度の高い展覧会であったといえる。」と総合的に評価している。(楠本亜紀Dog Mountain Report2013年2月) 清水氏も、インスタレーションとしての評価は変えていない。 「志賀理江子という作家の才能は、写真のなかにあるのではなく、写真を使う才能、写真で演出する才能なのである。」(同前) 気になるのは、〈追憶と喪が交代する舞台装置〉のことだ。 「喪」という語には死を穢れととらえる考えがあり、喪に服すとは死の穢れに触れた者つまり近親者が忌み慎むことである。 観客を服喪に誘う空間を作るために、志賀さんがインストールしたのは、なんだったか。さまざまに加工したり演出した映像は彼女のイメージというのだが、・・・・・・ 清水氏は検証している。 「螺旋海岸」が東北大震災の「ドキュメンタリーではない」という付言が繰りかえされ、それでいて、なんとか作品と被災地を結びつけようとして大量の言葉が空しく投入されるという奇妙な事態が出来しているわけだが、(中略)別の言い方をすれば、シュールリアリズム、ドキュメンタリーが形骸化・通俗化した姿が心霊写真でありホラー映画なのである。」(同前) 彼女がインストールしたのは、震災・津波災の〈記録〉だった。 写真の一つの特性〈記録〉に、どう対処するかは、写真家にとっての岐路でもあるが、単に手法の選択ではない、写真家の資質や感性のことかも知れない。土門拳か、ウジェーヌ・アッジェか。つまり、いろいろ工夫や演出を試みながらもリアリズム写真になってしまう土門流と、パリ市の依頼で撮影しただけの、古い建物の記録写真から妖気が漂ってくるアッジェ風のことだ。 乱暴な言い方だけれど、記録がアッジェ風ならシュールレアリズムに行き、土門流の記録ならドキュメンタリーの方へ傾く。 志賀さんの技術を尽くした仕事も、この路から離れることは出来なかった。(つづく) |
 |
 |