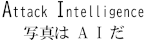 |
 ジーンズは立ち止まり、黒い仮面を顔から剥がして、今度はきょろきょろ肉眼で見はじめる。口元に優しい笑みを浮かべて・・・・・・。 北条裕子さんの『美しい顔』の冒頭のシークエンスを読んで、胸に何らかの反応を覚えなかったカメラマンはいないだろう。 何らかの反応、の中身はおそらく2つ。 1,この姿、獲物をかぎつけるハイエナか。われながらさもしい姿。 いたたまれない。被災者に対して後ろめたい。自己嫌悪。 2,もっと堂々とカメラを構えろ。写真の真髄は記録である。事件であれ災害であれまず現場に行き、この目で見て記録する。カメラマンの鉄則だ。 1950年代に土門拳が主導した「絶対非演出の絶対スナップ」のリアリズム写真は、日本の近代写真の最もアカデミックな作法であり、伝統的な精神論でもある。 『遺体 震災、津波の果てに』(新潮社刊)を上梓した石井光太氏は、3月11日当日、東京の自宅で原稿を執筆中だった。激しい揺れで、急いでテレビを点け、津波の映像を見て、「即座に私は現地へ赴く決心をした。理由は二つある。一つは物を書いている身として(中略)大惨事をこの目に焼き付けなければならないと思ったこと。二つ目は(中略)現場を見ずに筆を取るのは読者ばかりでなく自分に対する裏切り行為に等しいと考えたことだ。」(あとがき「取材を終えて」より)「取材を開始したのは週が明けた3月14日だった。」 北条裕子さんもその日、東京にいた。群像新人賞の「受賞の言葉」で、「実際、私は被災地に行ったことは一度もありません。」と告白する。「・・・・何もかもが怖くて、下宿で布をかぶってテレビを見ていたのです。」 「時が過ぎ、テレビでも震災のことをあまりやらなくなってから」、彼女は考えはじめる。そしておそらくそのころから出始めた記録・調査資料を読み、「被災者ではない私が、震災を題材にし、それも一人称で」書き始めるのである。 読みながら、これはロラン・バルトが「明るい部屋」の中ですでに解説しているではないか、と思う。 バルト氏は書いている。「私は・・・・写真が三つの実践(三つの感動、三つの志向)の対象となり得ることに注目した。すなわち、撮ること、撮られること、眺めることである。」 カメラに収められた「記録」は、メデイアに出ることで「情報」となる。しかしカメラが記録したはずの、泥を咥えた断末魔の顔面や、電柱にしがみついた姿勢のまま硬直した遺体は絶対にメデイアには出てこない。 情報はフィクションだ、と彼女は理解する。 リフレーンを効かせた文体に胸を強く連打されながら、東松照明氏の言葉を思い出していた。それは、うろ覚えだが、「医者は病気を治すことが出来る。弁護士は訴訟を助すけることが出来る。写真家は何も出来ない、ただ見るだけだ」。 名言だとは思っていたが、見るだけ、は〈見るという地獄〉のことだったのか。カメラマンの端くれの者でも全身が総毛立った。さらに、「浄土とは、曇りなき目で見られた地獄のことなのだ」(辻原登氏、新人賞の選評より)という言葉に出会う。 これはもう冗談ではなく、あわててAI搭載のカメラのレンズを拭くしかない。 マスコミは探している少女を追う。しかし読者は、もう母は生きていないことを知っている。当の少女さえ知っていると感じている。 遺体がひしめく体育館で、少女は母に遭う。失った下半身にスカートを巻きつけ、半分しかない顔をきれいに化粧した、美しい顔に。 体育館のドームに響きわたる少女の叫びを、読者は涙を流して聞く。黙々と歩く警官とうずくまる白衣の医師。トラックがきて新しい屍体が運び込まれる。 運ばれてきたのは屍体で、死ではない、と読者は気づく。ドームに充満しているのは、生が去り、死も消えていった抜け殻だ。 読者は、母の「美しい顔」に安堵する。そして、のちにそれは〈永遠の昨日〉の中にあることを知るのだ。 死は何処へ行ったのか? ふたたびロラン・バルトへ戻る。 「撮影者(オペラトール)」、「幻像(スペルトルム)」、「観客(スペクタトール)」について、 「スペルトルムというラテン語には、〈見世物〉あらゆる写真に含まれている、あの少しばかり恐ろしげなもの、つまり死者の再来=幽霊をもさすからである。」 またもこの小説を見事に解説しているようだ。 写真には死が含まれている。死は、生者の中にある。そうか、僕たちは気づかないうちに死を撮っているのか?影もない、見えないものを。 ならば、冒頭で書いた〈何らかの反応〉に三つ目があるはずだ。 3、現場には行かない。記録は、公的機関や警察の担当カメラマンに任せる。それら個人的感情の入らない記録は、創作のための貴重な素材であり、フィクションが飛翔する翼となる。 確かに小説では特に珍しくもない方法で、北条さんも成功している。が、写真では不可能な方法だと思われていた。 笑い話のようだが、うまくいけば、記録という罠を抜けきれば、〈見たこともない写真〉が出来上がるかもしれない、と強く思う。 母を失った日は〈永遠の昨日〉のように思う。少女は、自分の〈永遠の過去〉の顔を恋する。 読者には二つの「美しい顔」が重なって見えてくる。 「これから、いくどもいくども日常との戦いに敗れ、敗れ敗れて、もうこれ以上負ければ駄目だと思いながらも負け続け、・・・」 少女は、15メートルではない、日常という名の小さな津波の被災者となるが、もうダンボールの避難所もなく、マスコミも来ない。 「しかしやはり負け続ける以外に生きていく術がなく、それに気がついて絶望するのだろう。・・・・」 その通りだと思う。たまたま読者の一人にすぎないカメラマンも、日常に負け続けている。負け続けながら、日常にカメラを向けて小さなシャッター音を立てていくしかない。そろーりそろーりと日常のまわりを回りながら、絶望しながら。 〈見るという地獄〉が職業だから仕方のないことだ。 |
 |
 |