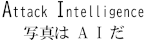 |
 『鎌鼬』を最初に視た時のことを思い出す。それはいわゆる写真集ではなく、物語の詰まった、秘密めいた、重いブツだった。奥付には、写真・細江英公 舞踏・土方巽 序文・瀧口修造 詩・三好豊一郎 造本・田中一光 現代思潮社版 とある。1968年の各ジャンルのキラ星たちが集まってわいわいやりながら1冊のブツを練り上げていく。そのイメージに激しく羨望したのだった。 ミュージアムの館長でもある細江さんは、通りすがりに立ち寄った、という風に現れて、そのままカメラの前に立った。直前まで難しい会議でもあったのか、何かほかのことを考えているようでもあった。 最初のシュートは、2004年7月31日14時15分47秒だった。カメラがデジタルになってから、データごとに撮影日時が記録されるようになった。 2003年、オリンパスカメラが、フイルムカメラの製造を中止して、デジタルの日本初の本格設計カメラE-1を発売した。いわゆる「デジカメの夜明け」だ。カメラ業界も変革の時代に入っていくのだが、そのE-1の宣伝広告シリーズ『物語の風景』の〈カメラを持った旅人〉写真と文を担当することになった。ちょうど雑誌「旅」が、JTBから新潮社に移った時だった。細江さんに登場をお願いしたのはその3回目だった。その文は、 鎌鼬の鳴き声は シャッターの音 大気中に小旋風が起って真空状態が生じた時、それに触れた肉が切り裂かれる、というカマイタチ。近ごろめったに聞かれなくなったのはなぜでしょうか? 1965年、細江青年と舞踏家の土方さんは、土方さんの故郷秋田へ向かいます。山形生まれで幼児から東京で育ち、戦時中山形に疎開していた細江さんは、「人間の生きる原点を忘れないため」、土方巽のドキュメントの撮影を始めたのです。 60年安保をめぐる騒乱を背負ったままでした。「絶対非演出の絶対スナップ」が写真の主流だった時代に、「絶対演出の絶対ドキュメント」を唱えて、シャッターを押しつづける細江さん。… さて、カメラマンならだれでも、連写の中で『写った!』と知らせる特別のシャッター音を聞くことがあります。 カメラを構えた旅人は、ふと気づきました。その特別な音こそ、カマイタチの鳴き声ではないか? と。 …その時、清里の深い緑に包まれたモダンなミュージアムの中で、人間の奥深い闇を切り裂くような、鋭い鳴き声に似たシャッター音をきいたのです。 1939年ごろに起こった土門拳と名取洋之助の論争、当時アサヒグラフ」の発刊などグラフ誌が興隆して、ただ記録するだけだった写真が〈報道写真〉と名を変えた時代だ。 名取が報道写真を「物語を語るための記号」として社会的なメッセージを伝えるツールといい、土門はリアリズムすなわち「絶対非演出の絶対スナップ」を提唱した。元々名取が犯した著作権問題が絡む怨嗟が加わって、名取側は土門をクソリアリズムと罵倒するなど泥試合になったらしいけれど、写真界は負けたはずの土門拳を城主に仕立てて「絶対非演出」の砦を築いていった。日本の写真にとって極めて重要な、―2024年の現在まで尾を引いている論争であった。 1968年11月には、中平卓馬、多木浩二、東松照明などが「思想のための挑発的資料」というPROVOKE誌を発刊。中平は「写真は記録である限り媒介に過ぎない」と土門派を挑発した。Provokeは、怒らせる、いらだたせる、の意味だが、絶対スナップ派はどこ吹く風で取り合おうともしなかった。論争は半分で終わったままだ。 「1968」は世界のあちこちで学生たちが既成秩序に向かって石を投げた年である。投げた後には、すべてが一瞬の夢だったことを知るのだが、PROVOKEの挑発は写真のリアリズムを問い直す貴重なチャンスだった。しかし、彼らのプレゼンテーション「アレ・ボケ・ブレ」は、安易に過ぎた、と思われる。それくらいの技術やスタイルで写真のリアリティが得られるはずがない。提案した中平が晩年に発表した退屈な写真が何よりの証拠だ。 独り、群れを外れて石を投げ続けている写真家がいた。67年からから土方巽と「鎌鼬」の創作に入った細江英公さんだ。 「・・・ただ一点だけ確認の時間を下さい。「絶対非演出の絶対ドキュメント」か「絶対スナップ」だったか、1968年の展覧会の時の「ご挨拶パネル」を調べて見る必要があります。・・・・」 8月9日の日付で2度目の封書。挨拶パネルのコピーと手書きのメもが届いた。 とてつもなく悲劇的な喜劇 日本の舞踏家:天才〈土方巽〉主演写真劇場 (前略)このたびの展覧会は、あくまでも、分かりやすい写真をお見せしたいと考えております。しかし、このような仕事は気がふれたときしかできないもので、 お互いの発作のたびごとにボツボツと撮りためてきたものであります。その意味でこれこそは絶対演出による日本の舞踏家・天才〈土方巽〉主演の、最も充血したドキュメンタリーであり、この〈天才〉の勃起を信じた写真家による熱血のフォトグラフィーであります。 (中略) 現在、土方巽40才、わたくし35才であることだけをつけ加えておきます。どうぞみなさま、ごゆるりとご鑑賞ください。(後略) 1968年3月細江英公 メモには、記事の宿題の箇所は「絶対演出による熱血のフォトグラフィー」でも「絶対演出による充血のドキュメンタリー」でも良いと繰り返して書かれていた。 キイワードは「絶対演出」だった。 1963年、三島由紀夫を撮った『薔薇刑』(集英社)(日本写真批評家協会作家賞) 1969年、「鎌鼬」(芸術選奨文部大臣賞) 2017年11月、旭日重光章受章。 ・・・経歴や受賞歴、名誉職その他は書き切れないが、作品歴をたどってみると、単なる写真集は見当たらず、 1952年、 「写真サロン」11月号、月例コンテストで『銀座の乞食の子供』が特選となる。 1956年、最初の個展「フォトストーリー・東京のアメリカ娘」はラジオドラマの原作になる。 2000年 『写真絵本[妖精物語]ルナ・ロッサ』(新潮社) など、物語や絵画などとの共作ばかりが目につく。土方さんとの共作も『鎌鼬』だけでなく『へそと原爆』などの映像がある。 最初の雑誌掲載が「乞食の子供」で、「おとこと女」、「薔薇刑」、「鎌鼬」のちの「抱擁」などを見ると、細江さんは人間を奥深く探検するために、からだから入っていく独特のドリルを手に入れた、それが写真の物語化、映像化、そして「絶対演出の絶対ドキュメント」の方法であったと思われる。初個展のフォトストーリーがドラマ化されたことは、細江さんの将来を鋭く予見していたのだろう。 1日1兆回超のスマホのカシャに、社会現象の瞬間を捉える「絶対非演出の絶対スナップ」を写真ごと奪われてしまったのだ。 「絶対演出の絶対ドキュメント」が情報を伝達して、人間と人間の会話を試みる方法だとすれば・・・・・、 細江さんは絶対演出の鎌鼬となって人のからだに分け入った。 鎌鼬の空気の反乱はやがて渦を巻いて竜巻になるはずだった。 残念ながら、9月16日、細江英公さんは逝ってしまわれた。 戻ってきて、巨大なトルネードを演出してほしいです。 |
 |
 |