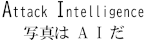 |
 AIの回答の後半を読むと、女王の名によるイギリスの悪辣な迫害の形相が彷彿とイメージされる。AIは意外に正直だ。 質問: ノーウーマンノークライのウーマンは、イギリスの女王のことだという説がありますが。。。。  「No Woman, No Cry」の「Woman」がイギリスの女王を指すという解釈は一般的ではありません。この曲の「Woman」は、ボブ・マーリーが生まれ育ったジャマイカのトレンチタウンというスラム街での生活を描いており、そこで苦境に立たされている女性たちを指しています。 ボブ・マーリーはこの曲を通じて、貧困や社会からの抑圧に直面している人々に対する慰めと希望を伝えています。そのため、「Woman」は、そのような困難な状況にある女性たち、または一般的に困難な状況にある人々を象徴していると解釈されます。 また、曲名の「No Woman, No Cry」は、ジャマイカの言葉で「Woman, don’t cry」を意味します。つまり、「女性よ、泣かないで」というメッセージが込められています。 以上の情報から、この曲の「Woman」がイギリスの女王を指すという解釈は、曲の背景やボブ・マーリーの意図とは異なると言えます。この曲は、ボブ・マーリーの音楽が生まれた原点となった場所、「トレンチタウン」という名のゲットーについて語っています。ボブ・マーリーは、レゲエという音楽を通じて社会をよくしたい、社会から押さえつけられている弱者である黒人、女性、子供たちを救いたかったのではと思います。この歌は、そんな弱者でこの町で迫害されてきたであろう”Woman”に呼びかけて、「泣いてはだめだ、奴らに油断してはだめだ、俺たちの仲間はみんな消されてきたじゃないか、もっと強くなるんだ」と背中を押しているように思えます。この曲は、ボブ・マーリーの音楽が生まれた原点となった場所、「トレンチタウン」という名のゲットーについて語っています。  |
 |
 |